人が健康を維持するために必要なのは、運動・栄養・休養の三つというのは有名ですね。
人の研究は様々な分野で研究されています。
運動については運動学で研究されているし、適切な栄養についても栄養学で研究されています。
しかし休養学というのはあまり聞きません。
実際に私のパソコンで「きゅうようがく」と入力すると旧洋楽が1番に出てきます。
休養が大切なのはみんな知っているのに、休養をしっかり学ぼうということは今までありませんでした。
そこで医学博士で日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏は【休養学】を広めようと活動しています。
今回のブログは片野先生の著書「あなたを疲れから救う休養学」の内容を抜粋してお伝えします。
休養を軽視する日本社会
片野氏の著書によると日本社会は休養を軽視しすぎだそうです。
- 「風邪をひいたから休みます」
- 「怪我で休みます」
は許されますが、
- 「疲れたから休みます」
と言って休める会社はまだあまりありません。

それが許される会社こそ生産性が高いのだと思います。
疲れたから休むというのは怠けやサボりだという意識が日本人の共通認識になっています。
逆に休まないことが美徳という感覚もまだまだ抜けきれていないのですね。
24時間働けません。
正直、私もちょっと前まではそういう感覚でした。
日本の休日は少ない?
では実際に日本人は休みが少ないのでしょうか?
実は労働時間が長いイメージのある日本人ですが、OECDで行った調査では年間労働時間は
- 日本1607時間
- OECD加盟国平均1752時間
と日本はOECD加盟国平均より短くなっています。
休みが多いことで有名なドイツは1341時間なので、ドイツと比べると長いですが、意外と労働時間は短い方なのです。
しかし平均睡眠時間は
- 日本 442分(7時間22分)
- OECD加盟国 508分(8時間28分)
こちらは平均と比べて1時間も短く、OECD加盟国中最下位でした。

労働時間は長くないのに睡眠時間が短いというのが日本の特徴のようですね。
休養も仕事の一部
一流スポーツ選手は疲労が溜まったらしっかり休養を取ります。
それは疲労状態だとパフォーマンスが低下するからです。
ビジネスマンも同様です。
疲労が溜まったまま仕事していたらパフォーマンスは上がりません。
疲れて休むのが社会人としてNGならば、パフォーマンスが低いまま仕事するのもNGです。
疲れているから休むはサボりではなく、真剣に仕事に取り組んでいる証拠です。
一方で発熱や怪我と違い、疲労は客観的データが出にくいのが難点です。
だからこそ疲労はマスキングされて(隠されて)しまいがちです。
マスキングしても疲労が消えるわけではありません。
いつか何処かで隠しきれなくなってバーンアウトしてしまいます。
早めの対応が必要です。
疲労の要因はストレス
疲労の原因になるのはストレスです。
ストレスと言っても嫌な気持ちになるものだけではなく、肉体的、精神的な疲労のもとになるもの全てがストレスです。
休養学ではストレスの原因になるストレッサーを以下の5つに分類しています。
- 物理的ストレッサー:暑さ、寒さ、騒音、混雑、振動など
- 科学的ストレッサー:公害、薬品、化学物質、アルコールなど
- 心理的ストレッサー:不安、緊張、怒り、悲観など
- 生物学的ストレッサー:細菌、ウイルス、感染、アレルゲン、ダニなど
- 社会的ストレッサー:家族関係、友人関係、人間関係、経済的問題など
これらが疲労の原因になっています。

色々なものが疲労の原因なんですね。
ストレッサーから受けた疲労を回復するためには正しい休養が必要です。
正しい休養・効果的な休養とはゴロゴロしたり、睡眠をとるだけではありません。
正しく効果的な休養については次回のブログでお知らせいたしますね。


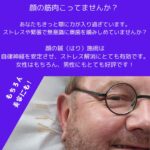


コメント